kakariだから、「使ってほしい」という熱意が伝わった。
~「寄り添う」が根付く薬局で、患者さんともっと近くに~
株式会社マル・コーポレーション
- 薬剤部次長
- 山崎 匡友 様
千草台ファーマシー
- 管理薬剤師
- 相川 哲也 先生
各薬局、それぞれの地域の名前を冠し た「地域密着型の”あなたの街のかかりつけ薬局”」として、千葉県内を中心に23の保険薬局を展開する、株式会社マル・コーポレーションさま。kakariは2022年2月に4店舗で先行導入、2022年7月に千草台ファーマシーさまを含む19店舗で追加導入いただきました。今回はkakari導入2か月で全社2番目のかかりつけ患者登録を達成した、千草台ファーマシー管理薬剤師の相川先生、そして本部でkakari導入を推進してくださった、薬剤部次長の山崎様にお話を伺いました。全社で大切にされている「寄り添う」が、日々の患者さんとの関わりや、kakariの対応に至るまで根づいていると感じられた取材となりました。
TOPICS 01患者さん一人ひとりに「寄り添う」。地域に根付いた薬局を目指して
ーー 相川
弊社では、「地域に根付いた薬局」を目指しています。薬剤師は、「患者さんの頼りになる存在でなければならない」、という考えを持っています。患者さんの薬や病気に関する悩みにしっかりと向き合い、応え、安心して薬を飲める様努めなければと思っています。
元々私は病院の方に勤めていました。当時、病院にいた頃は「調剤薬局って出来ることが少ないかも」と、思っていました。ところが、薬局に移って患者さんと話す機会がすごく増えたんです。病院では、薬と向かい合う時間がすごく多かったのですが、薬局では、「患者さんにどうやってうまく伝えるか」「どうやって話を聞いてもらえるか」と、人・コミュニケーションの方で勉強する部分が増え、転職前の先入観はすぐになくなりました。次第に地域の勉強会に参加したり、イベントに参加したり、薬以外の部分でも、仕事としてやれることが見つかって、そういった面で面白いなとやりがいを感じています。
ですので、普段のコミュニケーションでも、薬を渡すだけでなく、+αで患者さんのためになることを伝えられたらと思っています。その+αというのが世間話1個でも、患者さんに「あ、今日来てよかったな」と思って、帰ってもらえるといいなと思っています。
例えば、漢方薬って結構苦いですよね。大声では言えないですけど、中にはあまり推奨できない飲み方をされる方もいらっしゃるので、「こうやってお薬を飲んだら辛くないよ」と伝えたり。
薬と全然関係ない話もあります。「携帯のやり方教えて」とか。それこそ、kakariのやり方教えてくれ、というのもあります。それらに応えることで、患者さんも「薬局に頼ってよかったな」って思ってもらえるし、そういったものが次に繋がることもあるので断らないですね。
ーー 山崎
弊社として「寄り添う」という言葉をよく使うんです。
中でも相川さんは、患者さんの目線に立って、飲み方や、飲み忘れた時どうするかとか、その患者さんが実際飲む時に困るであろう所まで想像し、深く掘り下げていますね。そういった日々の対応が形となって、地域からも頼られる存在になっていて、弊社としても良い社員と出会ったなと思ってます。

TOPICS 02薬局に山積する、DXや服薬フォロー等の対応への課題。使いやすいから案内しやすい、kakariはすぐに浸透した。
ーー 山崎
kakari導入のきっかけは、今後進んでいくオンライン服薬指導やDXへの対応、あとは服薬フォローが義務化されたということでした。服薬フォロー、電話だとなかなか難しいこともあるので、気軽に話せて、相談できる機能があったらという点で選びました。
弊社では元々別の処方せん送信サービスも使っているのですが、kakariは管理画面の使いやすさと、患者さんへの案内の手軽さ、利用開始までのステップの少なさを比較すると、とても使いやすいんです。
よくある話ですが、皆「わからないもの」って使いたがらないんです。kakariは、実際に患者さんにアプリを操作しながら説明するスタッフもいるほどわかりやすく、患者さんへの案内もしやすいんです。元々使っていたサービスと管理画面も似ているので、これまでのサービスが練習となって、より簡単なkakariが入ったので、馴染みやすかった。
使っていきたい方向性と、使いやすさ、導入しやすさを全て総合してkakariを選んだのですが、社員の反応も良くて、沢山使ってくれていて、良いものに出会ったな、と思っています。
ーー 相川
これだけ浸透したのは、やっぱりサービスが良いからですよね。
私は初めてkakariの話を聞いた時点で、「今使ってるシステムよりも絶対いい」と感じました。山崎次長に「早くkakariをやりたい」と言ったくらいです。良いサービスな上、患者さんにお金はかからない。アプリダウンロード後の使い方も簡単だから、勧めたら皆良さに気づいてくれて入れてくれるだろう、と。
kakariはメインのボタンが2つだけで使い方が分かりやすいから、説明も簡単。私たちの“ぜひやってみてほしい”という熱意も患者さんに伝わりやすいです。スタッフ間でも、患者さんも薬局側も操作が簡単で、従量制ではなくコストが抑えられると、kakariを勧める納得感を得られました。
千草台ファーマシーでは、導入3ヵ月で約230名のかかりつけ登録。処方せん送信率は40%に。
ーー 相川
全体では、導入して1ヶ月目、7月時点で処方せん応需数が前年度と比較して5%増えて、8月は全部で12%増えてますので、kakariを導入した効果はすぐに出てきています。
門前の医療機関からの送信も多いのですが、それだけでは処方せんの増加にはなりません。私たちは、患者さまのお薬手帳に他の薬局の薬があったら、「この薬こちらでも用意できますよ。」と案内しています。その方が患者さんの待ち時間も減らせるし、薬を一元管理できるので、地域の方の他の医療機関の処方せんを持ってきてもらってますね。
案内は特にルール化していないのですが、皆投薬の1番最後にやってくれてますね。あと、人によって話を聞くタイミングって違ったりするので、なんとなく「今ここで勧めたら話聞いてくれるな」とか、逆に「あえて今日勧めない方がいいな」とか、見極めています。
気を付けているのは、案内した時の反応を記録に残しておくことです。例えば、「声掛けした/してない」は必須。あとは、「登録した/登録してない」とか。更に、「登録は難しそう」という人と、「登録してくれそう」という人。「登録してくれそうだけど、操作が難しいから次来た時に教えてあげる」というのは、ざっくりですがしっかり記録をつけています。そうすると、次回投薬する際、「kakari登録してくれた?」と話もできるので。中には1回目よりも2回目に納得して入れる方も一定数いるんですよね。
勿論、そういった前回患者さんがいらしたときの情報を記録することは、kakariに関わらず薬のお渡しという面でも大切にしています。
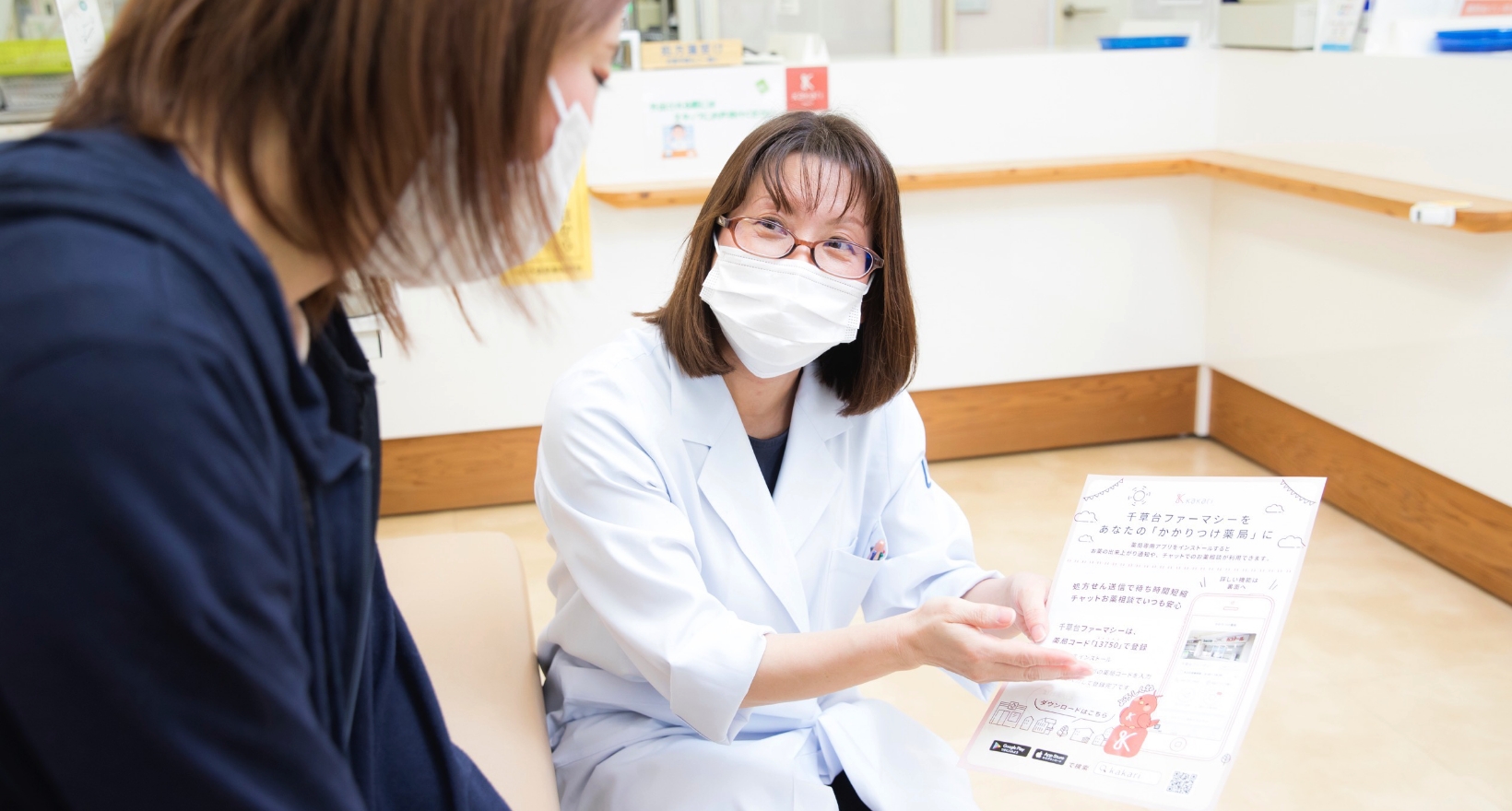
TOPICS 03kakariの案内も、一人ひとりの患者さんに「寄り添う」。スタッフの意識が根づいている。
ーー 相川
千草台ファーマシーは団地の中にあって、目の前にスーパーがあるような立地です。高齢者も多くて、ベースにある考えは「みんなスマホを使うのがそこまで得意ではない」。kakariは勿論入れたいと思ったのですが、「みんな登録できるかな」というのは、当初は内心不安でした。どうしようかと考えて、「本当に必要最低限なことだけやってもらおう」という方針になったんです。
具体的には、当薬局ではメールアドレスでのアカウント登録には力を入れていません。アカウント登録は機種変更時のお薬手帳情報引継ぎにしか使わないですが、うちの患者さんは紙手帳派の人が多いので重要度は高くないんです。また、高齢者の方はオレオレ詐欺等の影響でメアドや電話の登録に抵抗感が強いんです。そのため、kakariが推奨する「メールアドレス登録」という工程を削り、登録を更に簡単にしています。
更にスマホ操作が難しい方へは、「処方せんを送るだけでも大丈夫だよ」と言ってます。日付を決めたりしてくれたら私たちも楽ですが、「処方せんを送ってくれたら、準備出来次第連絡するからね。処方せんの送り方だけちょっと覚えてみて」と伝えています。
その分、どんな方にもkakariはメリットになるから、全員に声をかけてほしいとスタッフに伝えています。スタッフ目線で、絶対入れた方がいいよねという人を逃さないように。
例えば、子育て中のお母さんが風邪薬をもらいに来る場合、薬局に1回来て、スーパーに行って、また薬局に戻って薬を受け取って、更に他のことをして帰宅、という風になるんです。その往復が、子育て中のお母さんにはすごく大変なんです。だったら、その工程を1個省くことが可能なツールは使ってもらった方が良いですよね。
また、お話を聞いていると、他の人の薬を取りに来たり管理している人も、病院や薬局で待つのが結構苦痛かもしれない、と思うんです。やはり自分の薬ではないし、ご自身も仕事で忙しい中時間を空けて来ているので、待ち時間は本当にネックになっています。そういった方も、kakariを入れておけば、待ち時間がなくなりますしスムーズです。
ーー 山崎
相川さんは、患者さんの”くすぐる”ポイントを言うんですよ。処方せんを送る機能、相談できる機能、一遍通りではなく「この人多分これを求めている」というポイントを人によって変えているのは、上手だな、と思います。
ーー 相川
ただ効率を追求するだけなら、(人によって変えることなく)もっと簡単に出来ると思いますが、やるべきなのは「患者さんに寄り添う」ことだと思っています。患者さんがメリットになることを、頑張ってやっていきたいなという気持ちですね。他のスタッフも頑張ってくれていて、常に、「どう案内したら、kakariを使ってくれるかな」と、みんなで話し合ったりしていますね。「新しい何かをやって」という圧力ではなく、患者さんの負担をいかに軽減するか、kakariがどんなに便利か、納得感を持って伝えていったのが、大きかったです。

TOPICS 04患者さんと薬局が近くなる。地域で広がる「かかりつけ」のアプリ。
ーー 山崎
今度、千草台ファーマシーのある団地の依頼で、講習会を開催するんです。こういったご依頼を頂けるのも、日頃から相川さんやスタッフが、地域町ぐるみで頑張っているからだなと感じますね。
ーー 相川
その講習会のテーマが、「スマートフォンの使い方を学ぼう」なんです。なので、kakariのチラシからQRコードを読み取って、アプリのダウンロードを体験してもらおうかと思っています。その後は、ビデオ通話などアプリメインで使い方に慣れてもらおうと計画しています。
(高齢者とアプリの関わりと言えば)先日自転車で転んで左目を失明してしまった70代のおばあちゃんがいらしたんです。片目を失明してしまう位ですから、大分気分も沈んでしまっていて。
もともとスマホが得意な方ではなかったのですが、ミッションのような形でkakariを教えていったら、段々と覚えてくれました。そのうち、「写真ちゃんと送れたよ」と反応ももらえて、こちらからも「ちゃんと今日できてたよ」と言ったら、少しずつ明るくなってきたんです。今では毎回kakariで処方せんを送ってくれるし、以前より元気も出てきて、こちらも「勧めてみてよかったな」「明るくなって良かったな」って思います。
団地内のコミュニティも侮れなくて、患者さんが「kakariってアプリ、すごくいいよ」と、外の広場で他の住人に言ってるんですよね。それで、処方せんを持っていない方が薬局に入ってきて、「kakariってアプリ私もやりたいんだけど」と言ってくれることも。ついでにお薬手帳を見て、「この薬、うちでも渡せるよ」と、案内もしています。
チャット機能が、患者さんと薬局の距離を近づけている
ーー 相川
kakariの、チャット機能が便利なんです。画像もリンクも送れるので。それこそ飲み方の説明をしたり、「腰が痛いんだけど、どうしたらいい」という相談に対し、近隣の整形外科の情報をいくつか送ったりしています。
ある時、イソバイドが苦くて服用を躊躇されている患者さんに、工夫して飲んでもらえるよう参考になるサイトのリンクを送ったら、コンプライアンスが良くなったんです。その後来局されたときも、患者さんに「飲めたよ」とレスポンスもあって嬉しかったですね。
ーー 山崎
他の店舗でも、服薬時の飲み合わせのポイントを口頭で説明したものの伝わらなかったので、画像を添付したり。それで、「ありがとう」と返事を頂いたこともあります。
がんセンター門前の薬局では、疾患からやはり不安に感じられる患者さんが多いのですが、その不安をチャットですぐに相談できるんです。抗がん剤による副作用や発熱時の対応を相談されることもあります。
ーー 相川
チャットの返信は、薬剤師全員でそれぞれ手が空いたときにしていますね。みんな、患者さんに「寄り添う」という意識があるので、誰がやっても同じ回答をしてくれます。勿論忙しいと返事を返せない時はあるのですが、お昼とか手が空く時間帯はあるので、そういったタイミングで返事するようにしています。
ーー 山崎
チャットによって、患者さんは家にいながら薬局がすぐそこにあるような。私たちと患者さんとの距離がすごく近くなった気がします。
患者さんから相談されて「ありがとう」と言ってくれたら、やっぱり嬉しいですよね。だからこそ、チャットは一見手間かもしれないですが、手間ではないんです。我々も嬉しいし楽しいし、患者さんと話ができる、コミュニケーションが取れるって、良いものだなと思います。

TOPICS 05地域密着のスタンダードとして。kakariがあれば患者さんともっと近づける。
ーー山﨑
薬剤師が患者さんと話すときは、やっぱり薬のことが一番大事なので、アプリの案内で時間を取られたくないんですよね。その点kakariは本当に患者さんが使いやすくて簡単に紹介できるし、使い方も分かりやすいので、導入して損はないです。
kakariを他の薬局さんに勧めるなら、「患者さんと近くになれるよ」と伝えたいですね。これから更にDXが進んでいく世の中で、kakariを利用することで、患者さんが何でも相談できる、より使いやすく利用しやすい薬局になりたい。情報発信も更にしていくことで、もっと患者さんに近づけたらと思います。
ーー相川
オンライン化が進むこれからの時代、患者さんが薬局に来なくなってしまう可能性もあって、中々厳しい時代に入ってきていると思います。そんな中で、ただ薬を渡すだけではなく、「あの薬局さんに頼っておいてよかった」と、+αになることができればと思っています。kakariは、そういったサポートができるんじゃないかなと思うんです。
地域密着していく薬局って、今後どんどん増えていくと思います。そういった、地域密着のためのスタンダードなツールとして、kakariを入れることをお勧めします。
