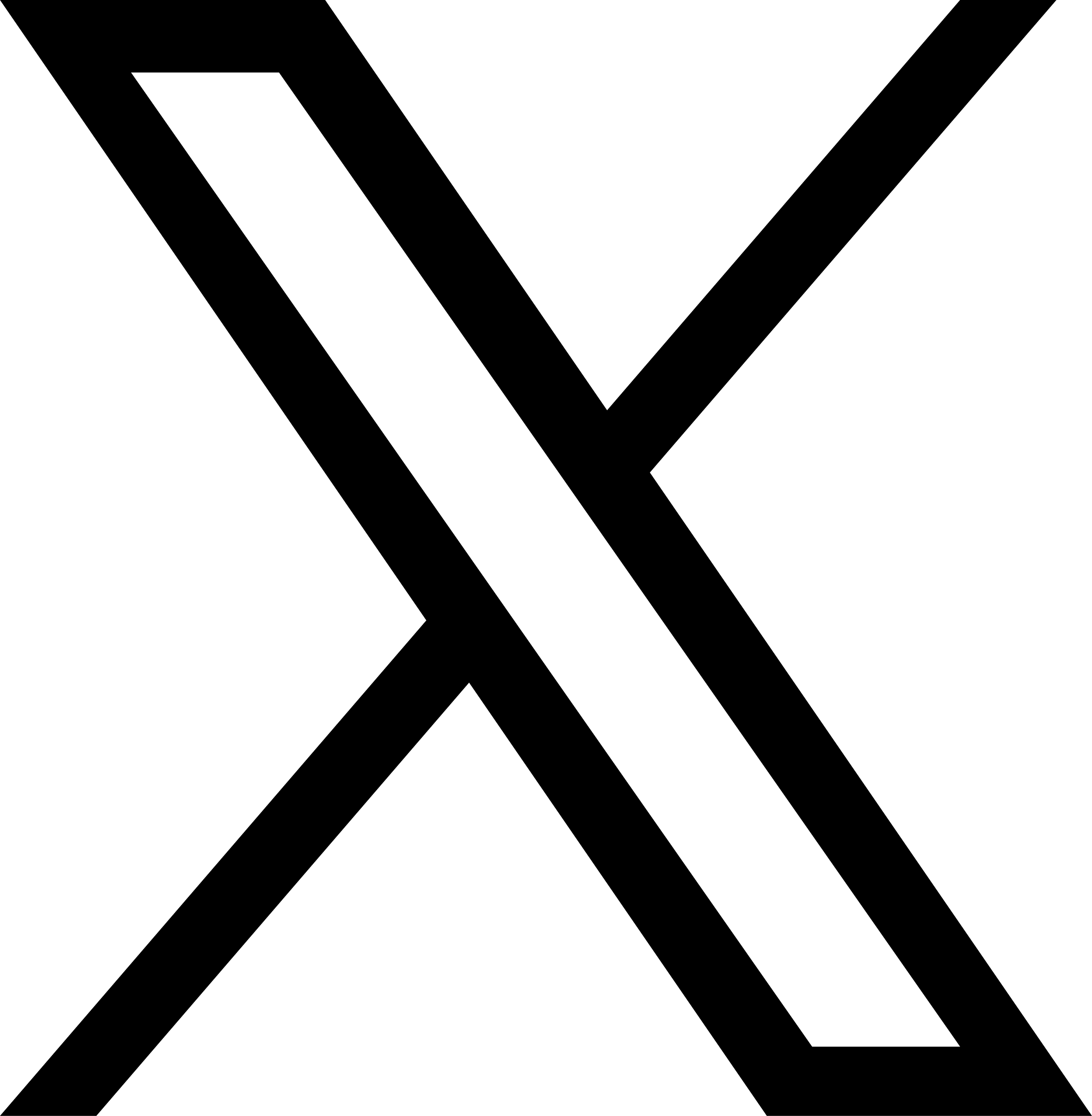2022年度(令和4年度)調剤報酬改定に準拠
服用薬剤調整支援料1
公開日2023/07/05
最終更新日
本ページの内容は、2022年度(令和4年度)調剤報酬改定の内容に基づいています。
最新の情報は、目次にある「他年度の改定内容」からご参照ください。
服用薬剤調整支援料1の点数
- 服用薬剤調整支援料1
- 125点
算定上の注意点
重複投薬等の解消に係る提案を行い、服用薬剤調整支援料2を算定した後に、服用薬剤調整支援料1の要件を満たした場合も、服用薬剤調整支援料1は併算定不可である。
関連項目
算定要件の要約
背景
- 薬局における減薬の取組に対する評価として2018年度改定で新設された。
- 算定にあたっては、いわゆるポリファーマシーの解消を薬局起点で行うことが求められており、患者の意向やアドヒアランス(注1)、副作用の可能性の検討を行い、それらトータルでの薬学管理を行った上で、処方医への提案を行うことが求められる。
- 開設当初は「減薬に至った結果」をもって算定できるとされていた。しかし、2020年度改定では、減薬に至らずとも提案をきっかけに、後に重複投薬等が解消したという実態が示されたことで評価が見直され、減薬に至った症例には「服用薬剤調整支援料1」を、提案に留まった症例には「服用薬剤調整支援料2」を算定可能として評価が2段階に変更された。
- 薬剤師としての職能が活きる点数項目であり、充実した薬局機能を評価する地域支援体制加算においても算定実績が求められるなど、重要度の高い項目である。
- 本点数項目は患者の意向を踏まえるなど、深い信頼関係のもとで行われるものであり、対人業務として今後さらに重要性を増すものである。
要点
- 患者の意向を確認した上で、当該患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討する必要がある。
- 減薬についてはそれ自体の実施がゴールではなく、減薬した状態での継続管理が求められる。そのため、減薬状況が4週以上継続した場合に服用薬剤調整支援料1が算定できることとなっており、患者に寄り添った対応が必要である。
- 配合剤や内服薬以外の薬剤への変更を保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない。

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。
算定要件の詳細
施設基準
なし
施設基準以外の算定要件
算定上限回数
月1回に限り所定点数を算定可能である。
算定対象患者
内服を開始して4週間以上経過しており、内服薬6種類以上を保険薬局で調剤している患者に対して算定可能である。
算定条件
①
上記の算定対象患者に対して、患者の意向を確認する。
②
当該患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討する。
検討を行うにあたって、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」(厚生労働省)、「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」(厚生労働省)、日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考にすること。
③
処方医に減薬の提案を行う。
処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに検討した薬学的内容を薬剤服用歴等に記載する。
- 保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴等に添付する等の方法により記録・保持する。
④
処方医への確認の結果、処方される内服薬が減少した場合について評価する。
当該薬局で調剤している内服薬の種類数が2種類以上(うち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定できる。
調剤報酬明細書の摘要欄への記載
算定にあたって、以下の項目を調剤報酬明細書の摘要欄に記載する。
- 保険医療機関名
- 保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数
留意点
服用薬剤調整支援料1を1年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から更に2種類以上減少したときに限り、新たに算定することができる。
注釈
注1 「アドヒアランス」とは
患者が積極的に治療方針の決定に参加し、その決定に従って治療を受けることを意味する。
補足
算定要件に記載されている「内服薬の種類」の考え方
錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。
以下の薬剤は「当該内服薬の種類数」に含めない。
- 屯服薬
- 浸煎薬、湯薬
- 内服薬の服用を開始して4週間以内の薬剤
- 調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤や内服薬以外の薬剤への変更を保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない。
服用薬剤調整支援料1についての原文
他年度の改定内容
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師
「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
執筆者のご紹介

執筆者:林 亜紀(はやし あき)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM
救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。
お問い合わせについてのご案内
当サイトでは調剤報酬に関する直接のお問い合わせには対応しておりません。調剤報酬算定に関する詳細な情報や具体的な質問については、厚生労働省またはお近くの地方厚生局に直接お問い合わせいただくようお願い申し上げます。
免責事項:当サイトに掲載されている情報の正確性には万全を期しておりますが、解釈に幅があるもの、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性がございます。利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、当社は責任を負いません。