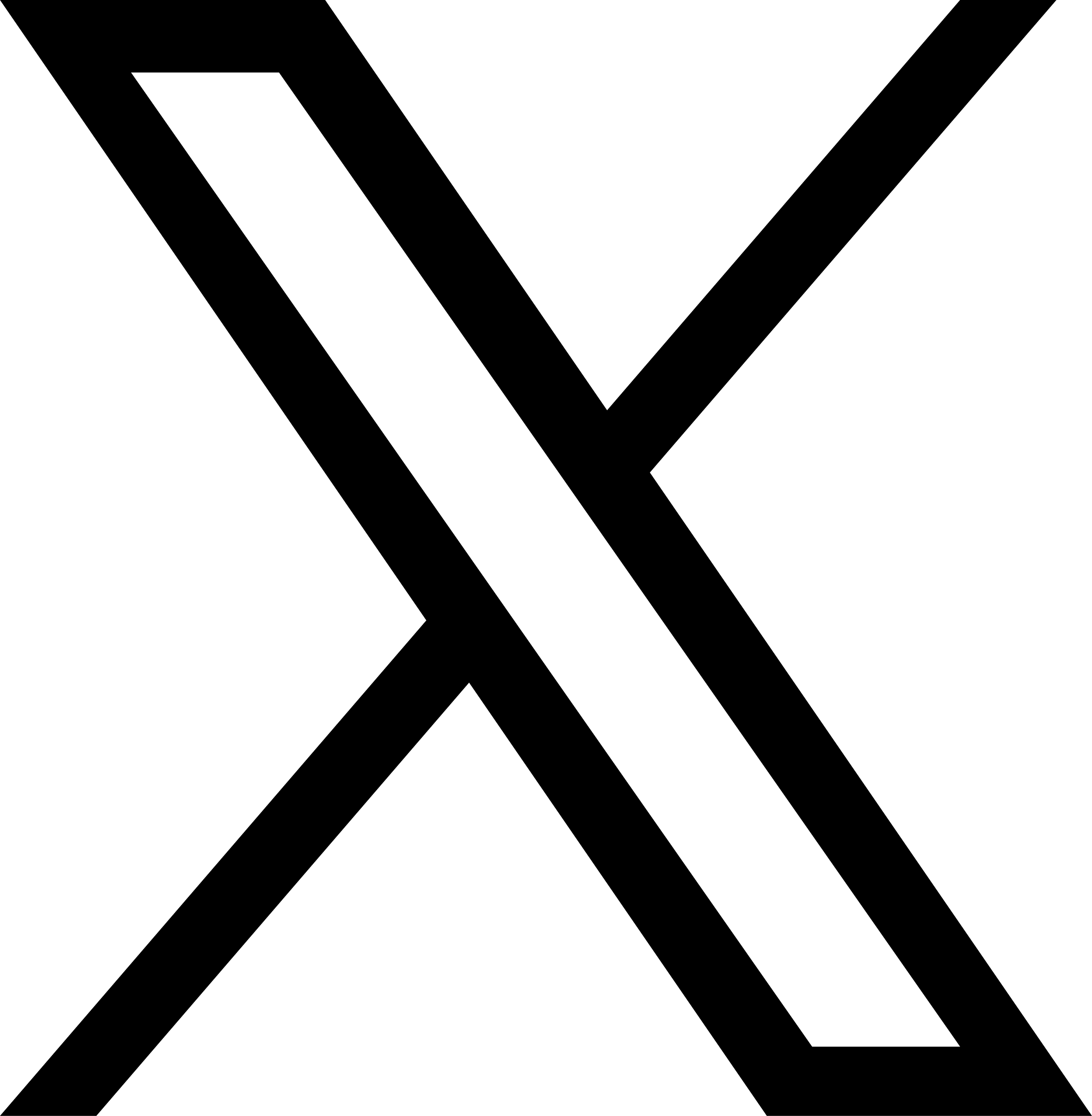2024年度(令和6年度)調剤報酬改定の内容に準拠
医療DX推進体制整備加算
公開日2024/05/30
最終更新日
医療DX推進体制整備加算の点数
- 医療DX推進体制整備加算1
- 10点
- 医療DX推進体制整備加算2
- 8点
- 医療DX推進体制整備加算3
- 6点
算定上の注意点
特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
関連項目
算定要件の要約
背景
- 令和4年10月に閣議決定された医療DX推進本部が進める「医療DX」のさらなる加速により、質の高い医療の提供を目的とし、その体制整備について2024年度調剤報酬改定から評価されることとなった。
- オンライン資格確認をはじめ、電子処方箋への対応やマイナ保険証の利用拡大への啓蒙活動など、医療DXによって進められるインフラの活用を目指した項目である。
- 令和7年には、医療DX推進体制整備加算の要件が見直された。その背景としては下記の2つが挙げられる。
1.
令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行したことや、これまでの利用率の実績を踏まえ、より多くの医療機関・薬局が医療DX推進のための体制を整備できるようにする。
2.
電子処方箋システム一斉点検の実施や、令和7年1月22日に示された電子処方箋に関する今後の対応を踏まえ、電子処方箋管理サービスへの登録の手間を評価する観点で調整する。
- 具体的な見直し内容はそれぞれ下記の通りである。
1.
令和7年4月〜9月のマイナ保険証利用率の実績要件を設定する。
2.
電子処方箋の導入のみならず、電子処方箋および紙の処方箋に基づく調剤の結果を電子処方箋管理サービスに登録することが求められている。
要点
オンライン資格確認により取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を評価する点数である。
算定要件の詳細
施設基準
体制要件
1.
電子レセプトによる診療報酬請求を行っていること。
2.
オンライン資格確認を行う体制(健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制)を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行う必要があることに留意すること。
3.
保険薬剤師が「オンライン資格確認」を通して患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧・活用できる体制を有していること。
4.
電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有すること。また、紙の処方箋を受け付け調剤した場合を含めて、原則として、全てにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録すること。
「電子処方箋により調剤する体制」とは?
「電子処方箋管理サービスの運用について」(厚生労働省 令和4年10月28日付、令和6年12月18日最終改正)に基づいて、電子処方箋を使って調剤し、調剤結果を登録できる体制のことです。
医療DX推進体制整備加算を算定するための条件:
- 電子処方箋システムの安全運用が確保されていること(例:医薬品マスタの適切な設定等)。
- 厚生労働省のチェックリストを用いた点検を完了していること。
- 点検完了後、指定の方法で報告すること(報告先:医療機関等向け総合ポータルサイト)。
調剤結果の登録について
調剤結果は、原則として速やかに電子処方箋管理サービスに登録する必要があります。数日分をまとめて登録するのは不可です。
理由:医療機関や患者が最新の薬剤情報を活用し、電子処方箋のメリットを最大限に得られるようにするため。参考情報
電子処方箋について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html電子処方箋管理サービスについて(医療機関等向け総合ポータルサイト)
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=c0252a742bdb9e508cdcfca16e91bf575.
電子薬剤服用歴等を管理する体制を有していること。
- 紙媒体で受け付けた処方箋、情報提供文書等を紙媒体のまま保管することは差し支えない。
- なお、保険薬局における医療DXによる情報活用等の観点から、オンライン資格確認、薬剤服用歴等の管理、レセプト請求業務等を担う当該保険薬局内の医療情報システム間で情報の連携が取られていることが望ましい。
6.
国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
7.
医療DX推進の体制に関する事項と、質の高い医療を提供するための十分な情報を取得・活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
(1)
オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧・活用している保険薬局であること。
(2)
マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険薬局であること。
(3)
電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施している保険薬局であること。
8.
原則として、「7.」の事項をウェブサイトに掲載していること。
- ただし、ホームページ等を有しない保険薬局については、この限りではない。
9.
最新の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照すること。また、「「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」や「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」等について」(令和5年10月13日付け医政参発1013第2号・医薬総発1013第1号医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官・医薬局総務課長通知)の別添1、別添2及び別添4を活用するなどして、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行う体制を有していること。
10.
マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に関する相談に応じる体制を有していること。
- 医療DX推進体制整備加算3を算定する場合、「10」は要件には含まれていない。
届出に関する事項
医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出は、 別添2の様式87の3の6を用いること。
- 上記「10」に関しては当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はない。
令和7年4月1日以降の医療DX推進体制整備加算の取扱いの変更に伴う事務手続きについては「 医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の見直しについて 厚生労働省 」をご参照ください。
実績要件
医療DX推進体制整備加算1
算定月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(注1)が以下の通りであること。
令和6年10月1日〜令和6年12月31日の間:15%以上
令和7年1月1日〜令和7年3月31日の間:30%以上
令和7年4月1日〜令和7年9月30日の間:45%以上
- 3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月(4月前)または前々月(5月前)のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることもできる。
医療DX推進体制整備加算2
算定月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(注1)が以下の通りであること。
令和6年10月1日〜令和6年12月31日の間:10%以上
令和7年1月1日〜令和7年3月31日の間:20%以上
令和7年4月1日〜令和7年9月30日の間:30%以上
- 3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月(4月前)または前々月(5月前)のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることもできる。
医療DX推進体制整備加算3
算定月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(注1)が以下の通りであること。
令和6年10月1日〜令和6年12月31日の間:5%以上
令和7年1月1日〜令和7年3月31日の間:10%以上
令和7年4月1日〜令和7年9月30日の間:15%以上
- 3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月(4月前)または前々月(5月前)のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることもできる。
マイナ保険証利用率について、以下の疑義解釈でより具体的に言及されています。
届出に関する事項
マイナ保険証利用率に関しては当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はない。
施設基準以外の算定要件
算定上限回数
処方箋受付1回につき、前述の「実績要件」に基づき、それぞれ加算する。
ただし、患者1人につき同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回のみの算定とする。
経過措置
- 令和7年9月30日までの間、電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制に関する要件を満たしているものとみなす。
- 令和7年9月30日までの間、体制要件の1つである薬局内掲示のうち、「(3)電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施している保険薬局であること。」の掲示を行っているものとみなす。
- 令和7年5月31日までの間、医療DX推進体制に関する事項等のウェブサイトへの掲載についての要件を満たしているものとみなす。
補足
オンライン資格確認の導入について
施設基準の1つでもあり、2023年4月から原則義務付けとなったオンライン資格確認の導入については、オンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局、システムベンダ向け)(厚生労働省)が参考になるので参照されたい。
注釈
注1 「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」とは
同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるもののこと。
医療DX推進体制整備加算についての原文
監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師
「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。
執筆者のご紹介

執筆者:林 亜紀(はやし あき)
メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM
救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。
お問い合わせについてのご案内
当サイトでは調剤報酬に関する直接のお問い合わせには対応しておりません。調剤報酬算定に関する詳細な情報や具体的な質問については、厚生労働省またはお近くの地方厚生局に直接お問い合わせいただくようお願い申し上げます。
免責事項:当サイトに掲載されている情報の正確性には万全を期しておりますが、解釈に幅があるもの、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性がございます。利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、当社は責任を負いません。